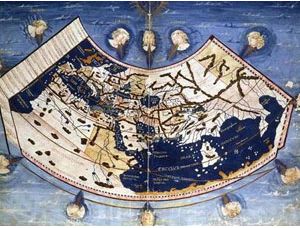♪
Gravity/ John Mayer
アイディア。
ふわふわしていて、ぐしゃぐしゃで、ばらばらで。
インタンジブルでつかめない。
ひねり出そうとすればするほど、するすると遠ざかっていくように。
手を伸ばせば伸ばすほどに、掌をすり抜けていくように。
意識は持っておくこと、アンテナは張っておくこと。
PARTYの中村さんが推薦していた図書『アイデアのつくり方』読みました。
アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない。
純粋なオリジナルなんてありえないんです。
コトバを話している時点で。
だれかに聞いたコトバ、本で読んだコトバ。
目にしたモノ、耳にしたモノ。
見たことのないモノ、聞いたことのないモノ、触れたことのないもの。
この世にないものから、この世にないものを創り出すのは不可能なのです。
それを認識することからアイディアの創成ははじまります。
コペルニクスが唱えた地動説も、進化論のダーウィンも古い学者たちの研究してきた学説を土台に自分の論にたどり着いているのです。
無数に散らばったアイディアのピースの相関性を看破し、体系づけてパズルを完成させたときはじめて1つのアイディアが生まれるのだと思います。
上記の図書の筆者であるジェームズ・ヤング氏はこう語ります。
事実と事実の間の関連性を探ろうとする心の習性がアイデア作成には最も大切なものとなるのである。
ヤングさんはアメリカ広告業界のトップをひた走っていました。彼は言います。
広告のアイデアは、製品と消費者に関する特殊知識と、人生とこの世の種種様様な出来事についての一般的知識との新しい組み合わせから生まれてくるものなのである。
本書では特に後者「一般知識」の重要性を特に強調していました。
一般知識とは要するに世の中に散らばるパズルのピースです。
何も広告に限ったことではなく、それこそ森羅万象すべてです。
興味の幅が広ければ広いほどいい。
だから、どれだけ広告を研究しても、秀逸なアイディアを分析しても関の山。
初対面でも朝まで飲み明かし、語るとわかりますよね。
哲学を持っている人なのか、否なのか。
自分の中に軸を持っていて、好奇心旺盛な人は楽にアイディアを生み出せるのかもしれません。
そしてアイディアが孵化する瞬間は至極なにげない瞬間であることがおおいとおっしゃっています。
とくにリラックスしている時。
お風呂に入っている時やソファで横になっている時。
ぼくなんかはタバコを吸っているときによく良いアイディアが思い浮かびます。そして瞬時にiPhoneにメモをとることにしています。
ぼくは大体、週5くらいアルバイトをしています。
時間が拘束されて、やりたいことができない。アルバイトをしていないほかの学生と差がついてしまう。
それは言い訳にはならないんじゃないかと思っています。
アイディアを生み出してくれるぼくの頭は、ぼくがどこにいっても何をしていても常にぼくのそばにいてくれます。
体が単純労働をしていても、頭を休ませるのも働かせるのもぼく次第なのです。
だからメモ帳とボールペンだけは常にポケットに忍ばせています。
点と点が繋がる瞬間は、ぼくの自由の効かない範囲の領域かもしれません。それはただぼくがまだ未熟なだけかもしれませんが。
ただ、その準備をしておくこと。全方位にアンテナを張っておくこと。種をまいておくこと。
それはぼくが意識すれば行えることです。
アイディアが宿る木には、肥えた土壌、適切な水やりと手入れ、良質な環境が必要なのかもしれません。